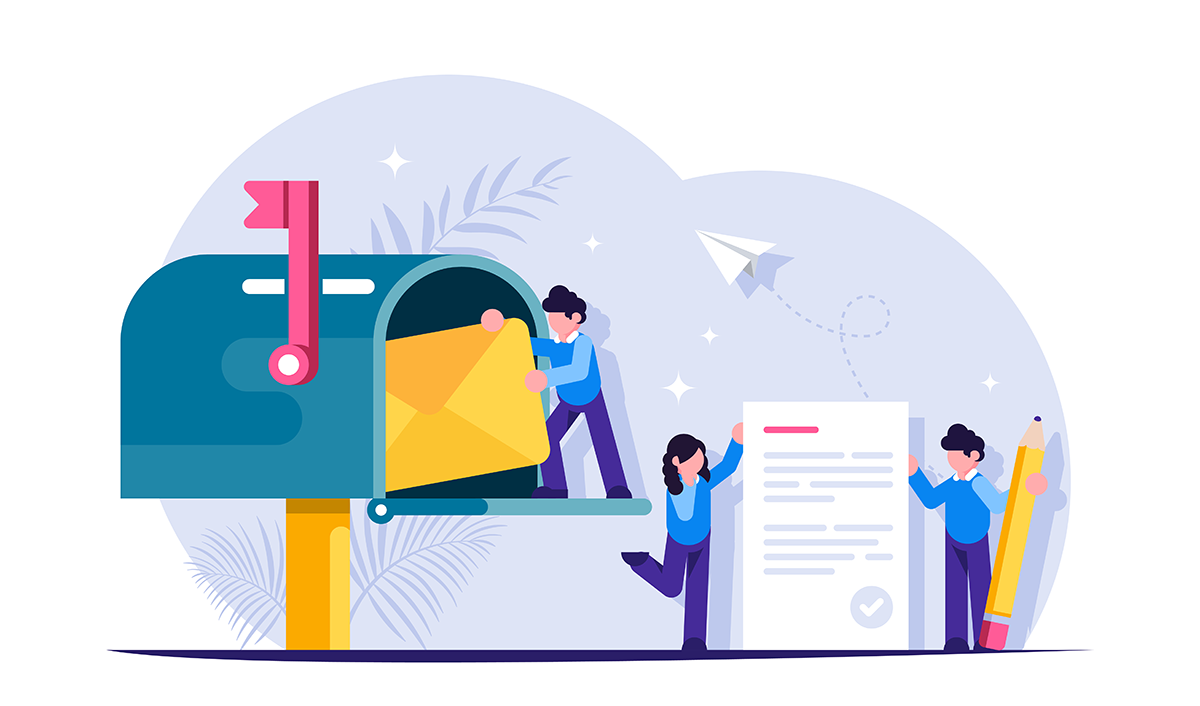BLOG ベアメールブログ
2024.05.23 (木)
HowToガイドメールのリストクリーニングとは? 具体的な実施方法、宛先リストの品質を保つポイントを解説

Last Updated on 2024.08.5
メール配信を行う宛先リストを精査することをリストクリーニングといいます。メールの到達率を高め、送信者レピュテーションを維持するためには、リストクリーニングが欠かせません。メールが届かない古いアドレスがリストに残っていると、様々な悪影響が発生するリスクがあります。本記事では、リストクリーニングの必要性や実施するタイミング、方法などについて詳しく解説します。
目次
メールのリストクリーニングとは
メールのリストクリーニングとは、メールを配信する宛先リストに古いアドレスや誤ったアドレスなどがないか精査し、無効なアドレスは削除することでリストを健全な状態に保つことです。
リストを作成してから長期間にわたって利用している場合、気付かないうちに無効なアドレスが増えてしまうことがあります。一般的には、入力時の人為的エラー、利用者によるアドレスの変更、アクティブではないメールアドレス、使い捨てのメールアドレスの使用などの理由が考えられます。そのため、定期的にリストをクリーニングして最新の状態を保つことが重要です。
リストクリーニングはなぜ必要?
適切にリストクリーニングを行わない場合、次のようなリスクが想定されます。
レピュテーションが下がる
大量のメールを配信する場合、宛先リストに含まれる無効なアドレスの割合が増えると、それだけ届かないメールが発生して配信エラー率が高くなります。エラー率の増加は、送信者の信頼性を表すレピュテーションのスコア低下にもつながります。レピュテーションが悪化してしまうと、評判の悪い送信者からのメールとして迷惑メール判定されるケースも考えられます。
レピュテーションについては以下の記事で詳しく解説しています。
IPレピュテーションとドメインレピュテーションとは? レピュテーション向上のポイントを解説 | ベアメールブログ
ブラックリストに入る
使われていない古いメールアドレスは、「スパムトラップ」になっている可能性があります。スパムトラップとは、迷惑メール送信者を炙り出すために用意された実際には使われていないメールアドレスのことで、過去に使われていたドメインやアドレスがスパムトラップとして再利用されることがあります。リストクリーニングを行わず、いつの間にかリストに紛れ込んだスパムトラップに誤ってメールを送信してしまうと、スパマーとみなされブラックリストに登録されてしまう恐れがあります。
ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
ブラックリスト登録されたメールの確認・解除方法について | ベアメールブログ
費用対効果が下がる
無効なアドレスにメールを送信し続けても、当然ですが顧客に読まれることはありません。せっかく手間やコストをかけてメールを作成・送信しても、効果が得られないため無駄になってしまいます。
リストクリーニングを行い、確実に届くアドレスのみにメールを送信することで、メールの到達率を向上させることができます。これにより、レピュテーションの維持やブラックリスト掲載のリスク軽減、そして費用対効果の改善など、多くのメリットが得られます。
メールのリストクリーニングを行うタイミング
では、どのくらいの頻度でメールのリストクリーニングを行うべきなのでしょうか。本章ではリストクリーニングを行うべき頻度や、別途行うべきタイミングについて解説します。
定期的なクリーニング
メールリストの規模や増加率にもよりますが、2〜3ヶ月に1回程度行うことが理想的です。少なくとも年に1〜2回程度は行うべきでしょう。
管理ツールを切り替えるとき
利用するメール配信サービスやCRM(顧客関係管理)ツールなどを新たなものに切り替える際は、データを移行する必要があります。そのため、リストクリーニングを行うよいタイミングといえます。
新たな宛先が大量に増えたとき
展示会やセミナーなどのイベント、マーケティングキャンペーンなどのきっかけで新たな購読者が一気に増えるタイミングにも注意が必要です。新しい購読者に対して一斉配信を行う前に、無効な宛先が紛れ込んでいないか確認するようにしましょう。
エラーメールが増加したとき
エラーメールには、次の2種類があります。
- ソフトバウンス:一時的なエラー。メールのサイズが大きすぎる、受信側のメールボックスが容量を超えているなど、原因が解消されれば届くようになるもの。
- ハードバウンス:永続的なエラー。宛先が存在しない、受信側サーバーにブロックされているなど、解消できないもの。
エラーメールが通常よりも増加した際には注視し、ハードバウンスのエラーであることを確認したらできるだけ速やかに対象のアドレスを削除しましょう。削除すべきエラーについては次章で詳しく解説します。
開封率・反応率が低いとき
メールの開封率が下がっている場合も、リストクリーニングに適したタイミングかもしれません。配信リストに無効な宛先が増えていないか見直してみましょう。
あるいは、配信に利用しているドメインがブラックリストに掲載されたり、レピュテーションが低下したりしたことで、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性が考えられます。メールが迷惑メールとして扱われてしまう要因は様々なため、改善のためには多角的なチェックと対策が必要となります。
迷惑メールとして判定されてしまう原因や改善策については、こちらの記事で詳しく解説しています。
迷惑メールだと判定されてしまう理由とは? スパム判定のチェックポイントと回避方法を解説 | ベアメールブログ
メールのリストクリーニングの実施方法
それでは、実際にメールのリストクリーニングを行う具体的な方法について解説します。
無効なアドレスを削除する
すでに変更されたアドレスや、入力ミスのあるアドレスなど、宛先不明のエラーが戻ってくるアドレスをリストから削除します。
エラーメールがソフトバウンスかハードバウンスか判断するには、メールのエラーコードを確認します。エラーコードは、エラーメールに記載される「3桁の数字+英文のメッセージ」で、次のように判断できます。
- 3桁の数字の1桁目が”4″の場合(4xx):一時的なエラー(ソフトバウンス)
- 3桁の数字の1桁目が”5″の場合(5xx):永続的なエラー(ハードバウンス)
メールのエラーコードについて詳しくはこちらの記事で解説しています。
メールのエラーコード(SMTPステータスコード)の意味と対策 – ベアメールブログ
バウンスのエラーコードやエラーメッセージを確認した上で、削除すべきと考えられるものは以下の通りです。
存在しない宛先(User Unknown)
ハードバウンスの中でも550や551、553などは宛先が存在しないことを表す代表的なエラーコードです。ただし、上記はあくまでRFC 5321で定義されている標準のSMTP応答コードであり、エラーコードを返す受信側メールサーバーによっては、同じコードでも異なるエラー内容を示す可能性があります。
除外すべきでない宛先を誤って削除してしまわないように、エラーコードではなくまずは「User Unknown」といった宛先が存在しないことを示すエラーメッセージで絞り込んで削除するのがお勧めです。
ドメインが間違っている宛先(DNS Error)
標準的なSMTP応答コードとしては定義されていませんが、一部のメールゲートウェイやメールサービスはカスタムエラーメッセージとして7から始まる3桁のコード(7xx)を返す場合があります。そのエラー内容が「I couldn’t find any host named DNS Error」といった、DNSが見つからない/名前解決ができないことを示す内容だった場合は、ドメインが間違っているということになるため、削除の対象として良いと考えられます。
捨てアドと考えられる宛先
一時的なエラーで再送を繰り返しても最終的に不達となってしまう宛先は、「捨てアド」と呼ばれる使い捨てのアドレスである可能性が高いと考えられます。そのためソフトバウンスについては、「◯回以上エラーとなったら削除する」といったルールを設けておくと良いでしょう。
管理用アドレスを削除する
主に企業で窓口として利用される「info@〜」「support@〜」といった管理用アドレスや窓口アドレスは、なるべくリストから排除します。
こうした役割に紐づくロールアドレスは、一般的に複数の受信者がアクセスするため、高いバウンス率やスパム苦情を引き起こしやすいというリスクがあります。
また、これらのロールアドレスは受信者から明示的な同意を得ずに収集された可能性が疑われます。未承諾の商用メール配信は、Spamhausなどのブラックリストサービスの判定基準となるガイドラインに反するため、ロールアドレスに対する大量メール配信はスパムとして扱われるリスクがあります。
再エンゲージメントキャンペーンを行う
メールサービスプロバイダは、メールを受信ボックスに届けるかどうかの判断のために、開封率などのエンゲージメント率も参考にしていると言われています。そのため、反応のない受信者がリストに増え、リスト全体の開封率が低くなってしまうことは望ましくありません。
反応のない受信者をリストから削除する前に、再エンゲージメントキャンペーンを実施してみることをお勧めします。再エンゲージメントキャンペーンとは、エンゲージメントが低い(開封率・クリック率が低い)受信者に対して、特典などを提供して関係性を復活させることを目的としたメールを送信することです。それでも反応がなかったユーザについてはリストから削除するようにしましょう。
メールの宛先リストの品質を保つためのポイント
最後に、メールの宛先リストの品質を保つため、メールリストの管理やメール配信に関して注意すべきポイントについて解説します。
ワンクリックで購読解除できるようにする
購読を望まない読者がすぐに購読解除できるよう、メールには必ず購読解除の方法(オプトアウト)を記載するようにしましょう。
メルマガなどの広告メールにオプトアウトの方法を記載することは、法律により義務付けられていることに加え、メールの到達率を維持するためにも重要です。オプトアウトの記載がない場合、ISPや携帯キャリア、メールサービスプロバイダなどに迷惑メールとして判定される要因となるだけでなく、購読を解除したい受信者によって受信拒否や迷惑メール報告されるリスクも高まります。
また、Gmailの新しい送信者ガイドラインにおいては、1日5000通以上Gmailに配信する送信者は、マーケティングメールにワンクリックでの登録解除機能を実装することを義務付けています。条件に該当する場合は、本文内にオプトアウトのURLを記載するだけでなく、List-Unsubscribeヘッダに対応する必要があります。
List-Unsubscribeについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
List-Unsubscribeとは? RFC8058の仕様に従って実装するポイント | ベアメールブログ
ダブルオプトイン方式を採用する
ダブルオプトイン方式とは、ユーザが登録のためにメールアドレスを入力した後、入力したメールアドレス宛に送られてくる確認メールに記載されたURLにアクセスして認証することで正式な会員登録ができる方式です。このように二段階の確認手続きを行うことで、登録意思の確認とメールアドレスの間違いを防ぐことができるため、メールアドレス登録の精度を上げリストの品質を高めるのに有効です。
まとめ
定期的にメールの宛先リストをクリーニングすることで、メール配信のエラー率を減らして到達率を高めることができます。リストに無効なアドレスが多く含まれていると、IPレピュテーションの低下や、ブラックリストに掲載されるリスクにもつながるため注意しましょう。しばらくリストクリーニングをしていない場合は、本記事を参考に実施することをお勧めします。